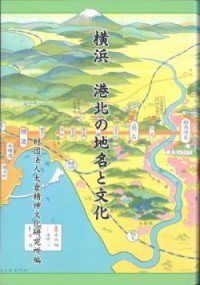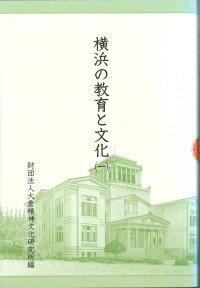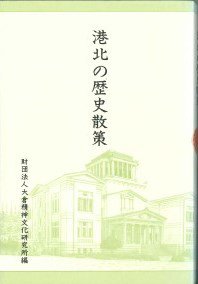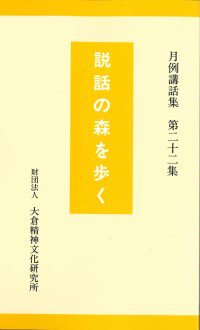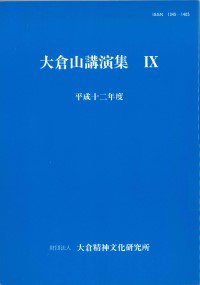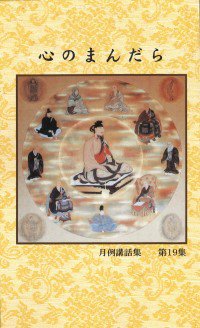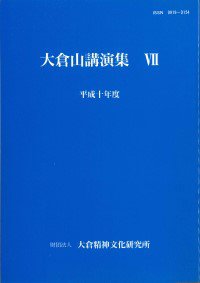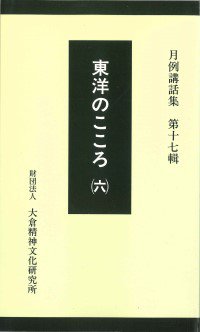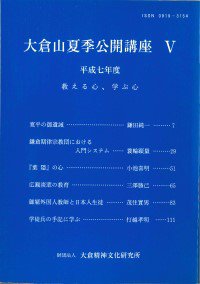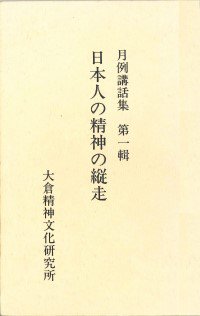各種講演録
大倉精神文化研究所が主催した講演会の記録集です。
各講演会の概要は、以下の通りです。
月例講話会 【完結】 本財団の研究員等が講師となり、一般市民を対象に行った講演会です。昭和62年(1987)4月から平成15年(2003)3月まで、全161回開催しました。
夏季公開講座 【完結】 本財団の創設者である大倉邦彦の命日(7月25日、三空忌)にちなみ、大倉山記念館以外の会場で実施した集中講座です。昭和63年(1988)より平成14年(2002)まで、全15回開催しました。
大倉山地域交流講座 【完結】 本財団の立地する横浜市港北区を中心とした地元地域の歴史や文化を紹介した講座です。毎年11月3日の文化の日の前後催される「大倉山秋の芸術祭」の期間中に開催しました。
-
- 講演集『横浜港北の地名と文化』
- 公開日:2009.03.24
-
- 講演集『横浜港北の自然と文化』
- 公開日:2006.05.16
-
- 講演集『武道精神とスポーツ精神(下)』
- 公開日:2005.03.01
-
- 講演集『武道精神とスポーツ精神(上)』
- 公開日:2003.07.11
-
- 講演集『横浜の教育と文化』(一)
- 公開日:2003.03.20
-
- 講演集『港北の歴史散策』
- 公開日:2003.03.10
-
- 『月例講話集』第22集
- 公開日:2003.03.07
-
- 『大倉山講演集』 Ⅹ 平成13年度
- 公開日:2002.03.08
-
- 『月例講話集』第21集
- 公開日:2001.07.18
-
- 『大倉山講演集』 Ⅸ 平成12年度
- 公開日:2001.03.08
-
- 『月例講話集』第20集
- 公開日:2000.07.15
-
- 『大倉山講演集』 Ⅷ 平成11年度
- 公開日:2000.03.10
-
- 『月例講話集』第19集
- 公開日:1999.07.25
-
- 『大倉山講演集』 Ⅶ 平成10年度
- 公開日:1999.03.25
-
- 『月例講話集』第18集
- 公開日:1999.03.20
-
- 『大倉山講演集』 Ⅵ 平成9年度
- 公開日:1998.03.24
-
- 『月例講話集』第17輯
- 公開日:1997.10.31
-
- 『月例講話集』第16輯
- 公開日:1997.03.26
-
- 『月例講話集』第15輯
- 公開日:1996.10.31
-
- 『大倉山夏季公開講座』 Ⅴ 平成7年度
- 公開日:1996.03.31
-
- 『月例講話集』第14輯
- 公開日:1996.03.25
-
- 『月例講話集』第13輯
- 公開日:1995.12.20
-
- 『大倉山夏季公開講座』 Ⅳ 平成6年度
- 公開日:1995.03.31
-
- 『月例講話集』第12輯
- 公開日:1995.03.25
-
- 『月例講話集』第11輯
- 公開日:1994.11.29
-
- 『大倉山夏季公開講座』 Ⅲ 平成5年度
- 公開日:1994.03.31
-
- 『月例講話集』第10輯
- 公開日:1994.03.25
-
- 『月例講話集』第9輯
- 公開日:1993.11.25
-
- 『大倉山夏季公開講座』 Ⅱ 平成4年度
- 公開日:1993.08.19
-
- 『月例講話集』第8輯
- 公開日:1993.03.31
-
- 『月例講話集』第7輯
- 公開日:1992.11.30
-
- 『大倉山夏季公開講座』 Ⅰ 平成3年度
- 公開日:1992.08.20
-
- 『月例講話集』第6輯
- 公開日:1992.03.31
-
- 『月例講話集』第5輯
- 公開日:1991.11.20
-
- 『月例講話集』第4輯
- 公開日:1991.03.31
-
- 『月例講話集』第3輯
- 公開日:1990.12.10
-
- 『月例講話集』第2輯
- 公開日:1990.03.31
-
- 『月例講話集』第1輯
- 公開日:1989.07.25