【新着図書より】8月上旬のおすすめ
- 2025.08.01
-
- 新着本
8月上旬公開の新着図書より、おすすめの4冊をご紹介します。
1 『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』 飯田一史 著 (請求記号:024.1-イ) 
かつて、駅前の一等地には本屋が必ずあり、ふらっと寄っては雑誌や文庫、コミックスを買ったものだった。だが、気がつけば町から本屋が消え、「わざわざ出掛ける場所」になってしまっている。いつから、どのようにして「町の本屋」はなくなってきたのか?出版流通の課題を歴史とデータから読みとき、戦後、書店がたどった道を明らかにする。
2 『近代万博と茶 世界が驚いた日本の「喫茶外交」史』 吉野亜湖・井戸幸一 共著 (請求記号:619.8-ヨ) 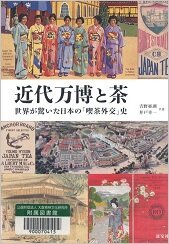
明治~戦前期、日本は国を挙げ、「外貨獲得の有効手段」として日本茶の海外展開に力を入れていた。日本茶文化は世界でどう受け入れられたのか?文化交流の随一の場だった万国博覧会での茶の扱いに着目、近代史の新たな一面を掘り下げる。
3 『飛脚は何を運んだのか―江戸街道輸送網』 巻島隆 著 (請求記号:693.2-マ) 
例えば、ベストセラー作家の曲亭(滝沢)馬琴は、誰と、どんなやり取りをしていたか。手紙だけでない飛脚が運ぶ物産、飛脚問屋の金融的な機能や全国津々浦々の情報流通に果たした役割とは。自然災害や事故、強盗等の被害にどう備えていたか。近代郵便制度の導入以前でも、全国につながる街道、江戸市中に張り巡らされた飛脚ネットワークは相当にすぐれていた。飛脚の成り立ち、制度の変遷、ビジネス化成功の裏話、やり取りされた手紙の内容まで、江戸時代の輸送の全貌を解き明かす。
4 『増補版 戦時下の絵本と教育勅語』 山中恒 著 (請求記号:726.6-ヤ) 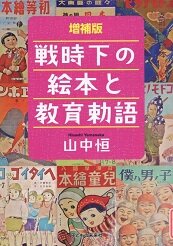
たくさんの絵本を紐解き、教育勅語の精神をどのように子どもに教えこんでいたかを検証する。あわせて勅語の歌や教科書も紹介し、戦後80年の今、改めて戦争と教育を考える。真珠湾攻撃の絵本と著者インタビューをカラーで増補。